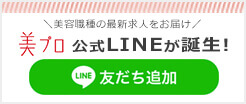ネイリストが持つべき資格について!種類や難易度、勉強方法など

Nobuyuki Kondo / ネイルアート (from Flickr, CC BY 2.0)
「ネイリストになろうかな!」と思いついた時に、考えることとして「資格取得」が挙げられるのではないでしょうか。就職する上で有利に働くだろう…と容易に考えられますし、技術に自信がない人にとって試験勉強は、ネイリストのスキル構築にも繋がります。
ネイルサロンの求人情報を見ると、ネイリスト資格を必須としていないサロンも多いのですが、サロンへ訪れるお客様の信頼を得ることができます。資格保持者を募集しているサロンでは、検定級の指定があることもあれば採用時に優遇してもらえることもあります。
持っていて損はないネイリストの資格ですが、どのような種類があるのか、資格を取るためにはどうしたら良いのかを、細かく説明していきます。また、資格試験を受ける上で、大変だなと感じる部分などを実体験からご紹介します。
INDEX
■ネイリストの国家資格について
■ネイリストの資格試験はどんなもの?
■ネイリストの資格や検定の種類
■ネイリストの資格・検定の受験費用
■ネイリストの資格試験や検定は何歳から受験可能?
■ネイリストの資格を取得するには?
■ネイリストの資格・検定の勉強方法
■ネイリストの資格取得・検定合格までに要する時間
■ネイリストの資格の難易度
■ネイリストの資格を取得するメリット
■ネイリストの資格がないと就職できない?
ネイリストの国家資格について
美容業界でいうと、美容師や理容師の資格が国家資格であるように、「ネイリストの資格はどうなのか?」と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。
日本では、ネイリストの国家資格はありません。ネイリストを目指す人の間では耳にしたことがあると思いますが、「JNECネイリスト技能検定」や「JNAジェルネイル技能検定」も国家資格ではなく民間資格となります。
民間資格ではありますが、ネイリスト業界で技術レベルを証明するには、この2つの技能検定がメインとなります。3級から1級まであるネイリスト技能検定では、1級を持っていれば人に教えられるくらいになりますし、2級を持っていれば多くのサロンに就職が可能です。ジェルネイルをメインにネイリストとして仕事をしたい人は、ジェルネイル技能検定も受けておくと良いでしょう。
- JNECネイリスト技能検定1級
- 講師レベル
- JNECネイリスト技能検定2級
- ネイルサロンへ就職できるレベル
技術の高さを測るとしたら、このような認識で良いでしょう。どこまで目指すかは人それぞれですが、「ネイリストになってお金を稼ぎたい!」という方は、ネイリスト技能検定1級を目指していくと良いですよ。
そして、ネイリストの活躍は日本だけに留まらず、諸外国でもネイリストの存在があるのです。諸外国のネイリスト資格はどのようになっているのでしょうか。
海を渡り、アメリカではネイリストの国家資格が存在するのです。アメリカでは、「マニキュアリストライセンス」といい、働く州によってライセンスを取得しなければなりません。日本のように、全国共通ではないのも特徴の一つです。ネイリストとして、国家資格取得を目指すのなら、アメリカに渡ってみても良いかもしれませんね。
ネイリストの資格試験はどんなもの?
ネイリストの資格試験はどのようなものなのでしょうか。初めて受験する人は、緊張して眠れないこともあるでしょう。試験は、筆記試験と実技試験で構成されていることが多いのですが、どのようなものなのかを把握しているだけでも、当日は安心して受験できますよね。全てではありませんが、この記事から少しでも試験の雰囲気を感じ取ってくださいね。
会場の雰囲気は?
試験会場といえば、学校のようなところを想像する人も多いでしょう。受験する試験によってことなりますが、JNECネイリスト技能検定では全国で多くの受験生が一斉に試験をうけるので、大規模な会場(ホール・催事場など)を使うことが多いのです。年に2回(1級)もしくは4回(2級・3級)しか開催されない試験ですので、そこで合格できるように勉強してきます。東京の試験会場では、午前と午後にわけて受験するのですが、およそ1,000人以上の受験生が同じ空間で一斉に試験を開始します。全国で、2級と3級だけでも9,000人以上の受験者数となった年もありますよ。
JNAジェルネイル技能検定では、お住まいの地域から通える範囲の会場を指定されることが多いのですが、その中でも美容専門学校が試験会場となることがあります。各教室に20人ほどの受験生が、教室に分かれて受験します。
取得する資格によって会場となる施設は変わりますし、住んでいる地域によっても変わります。大規模会場でも小規模会場でも、当日は力を発揮できるように備えておきましょう!
試験管はどんな人?
試験管は、認定講師などのネイリストであることがほとんどです。サロンワークを現役でしているネイリストやネイルスクールの講師など、ネイルに携わっている人が試験管となるため、審査が厳しく行われると考えていて良いでしょう。
試験中は、特に厳しく、荷物の位置や私語など、注意ポイントに目を光らせています。受験生のマナーが悪いと、減点もしくは失格となるため、試験を受ける前からチェックしているのです。
また、試験中には多くの試験管が、チェックシートを持って受験生のまわりを歩きます。実技試験においては、項目ごとでチェックする人が変わるので、一人の受験生に対し何人もの試験管がチェックしにやって来るのです。当日は、試験管に注意されることのないように、事前に減点項目と失格項目を頭に入れておきましょう。
受験生はどんな人?
ネイリスト資格試験の受験生は、ネイリストとして働いている人だけでなく、学生や社会人、主婦などと様々です。年齢は、義務教育を卒業した人であれば制限はないので、幅広い世代の受験生がいると考えていて良いでしょう。
また、検定級によって受験生の層は変わる可能性があります。はじめに受ける検定級であれば、スクール生や趣味でセルフネイルを楽しむ人、ネイルサロンに未経験で入社した人などが考えられます。しかし、検定級が上がるにつれ現役のネイリストである可能性が高くなります。中には、コンテスト受賞者やネイリストとしての経験が豊富な人もいることでしょう。
どんな状況に置かれている人でもチャレンジできる資格試験です。まわりを気にしがちな人は、自分のことだけに集中して試験に向き合ってくださいね。案外、みなさんは試験中に他の人を気にしていないので、自分の世界に入って取り組んでも問題ありません。
試験で使う道具はどうするの?
ネイリストの資格試験では、自身の道具を使用します。そのため、忘れ物なんてしまえば命取りです。指定されている道具を忘れてしまえば失格になってしまいます。また、指定されている道具以外のものを持ってきてしまうのも失格となります。試験会場で、使用するジェルを指定商品申請用紙に記入しますので、筆記用具も忘れずに持っていきましょう。
試験管が道具のチェックをできるように、ひとつひとつにラベルを貼るのも義務付けられています。ネイルショップに検定用のネームラベルが販売されているのですが、自作のネームラベルでも問題ないようです。ネイルスクールの講師などに確認しておくと良いでしょう。
また、試験当日にはなるべく新品を持っていくと良いでしょう。試験までの間に、何度も練習をするため、ポリッシュが固まりはじめてしまうことが予想されます。そうなると、綺麗に塗ることができないので合否に影響が出てしまいます。試験用として新品を用意し、家で1度だけ新品を使って練習し、問題がないことを確認してから試験に挑むと良いですよ。ジェルネイル検定では、ジェル筆が当日に毛先が広がってしまうアクシデントに注意しましょう。
ハンドモデルについて
ネイリストの検定試験を受けるにあたり、ネイリストの悩みの種でもあるハンドモデル。新型コロナウイルス感染症が流行した後は、人の手ではなくトレーニングハンドを使用することもありますが、それまでは人の手を使って試験を受けています。
ハンドモデルを頼むのは誰でも良いわけではなく、信頼をおける人にお願いすると良いでしょう。というのも、試験ではモデルのマナーや遅刻、私語などもチェック対象になるからです。試験当日まで、何度も何度も練習を重ねて来たのに、「モデルが来ない!遅刻!?」というようなことがあれば失格になります。受験費用も戻ってきませんし、次の試験日まで資格取得はお預けということになるのです。
また、爪や皮膚の状態も気にするべきポイントです。爪まわりの皮膚に疾患が認められる方は、ハンドモデルになれません。検定要項にも、そのあたりはしっかり記載されているので、ハンドモデルを頼む際に十分に注意しましょう。
ネイリストの資格や検定の種類
ネイリストの資格や検定は、さまざまな団体から発行されています。たとえば、インターナショナルネイルアソシエーション(I-NAIL-A)の認定する「ネイルスペシャリスト」や「ジェルネイルスペシャリスト」はよく知られていて、ネイリストとしてステップアップするために利用する人が多くいます。ネイルスペシャリストでは、ネイル全般の知識と技術を問う試験が行われ、そのランクはA級・SA級・PA/AA/AAA級の3つに分かれています。
また、最も有名なのはJNEC公益財団法人日本ネイリスト検定試験センターが主催する、「ネイリスト技能検定試験」です。1級から3級まであり、プロとして活動したいなら2級以上を取得するのがおすすめです。基本となるネイルケアやネイルアートに関する技術はもちろん、サロンで通用するレベルのスキルを習得できるようになっています。JNEネイリスト技能検定3級は、義務教育修了者ならだれでも受検することが可能なので、まずは地道に3級から目指しましょう。
日本の資格
JNECネイリスト技能検定3級
- 受験料
- 6,800円
- 受験資格
- 義務教育を修了していれば誰でも受験可能
- 試験開催日
- 冬季(1月)、春季(4月)、夏季(7月)、秋季(10月)の年4回
- 試験会場
- 東京、仙台、盛岡、大阪、札幌、福岡、名古屋、金沢、新潟、広島、高松、沖縄
- 試験内容
- 3級で必要とされるのは、ネイルケアやネイルアートに関する基本的な技術及び知識です。実技では、器具の基本的な使用方法や、正しい工程で出来ているかなどが審査の対象になります。
- できるようになること
- ネイルケア、ネイルアートに関する基本的な技術及び知識を修得していることを証明できる資格です。
関連記事:ネイリスト資格の代表格「ネイリスト技能検定試験」に迫る!
JNECネイリスト技能検定2級
- 受験料
- 9,800円
- 受験資格
- 3級に合格している者
- 試験開催日
- 冬季(1月)、春季(4月)、夏季(7月)、秋季(10月)の年4回
- 試験会場
- 東京、仙台、盛岡、大阪、札幌、福岡、名古屋、金沢、新潟、広島、高松、沖縄
- 試験内容
- 2級で求められるのは、サロンで働く場合でも通用する知識と技術。3級でチェックされたポイントもより細かく審査されるので、高い技術が必要です。
- できるようになること
- サロンワークで通用するネイルケア、リペア、チップ&ラップ、アートに関する技術及び知識を修得していることを証明できる資格です。
JNECネイリスト技能検定1級
- 受験料
- 12,500円
- 受験資格
- 2級に合格している者
- 試験開催日
- 春季(4月)、秋季(10月)の年2回
- 試験会場
- 東京、仙台、盛岡、大阪、札幌、福岡、名古屋、金沢、新潟、広島、高松、沖縄
- 試験内容
- 1級で求められるのは、完成品がキレイに出来ているかどうかだけでなく、均一に仕上がっているか、色彩やデザインなどが優れているかという点などを重視した基準となっており、技術だけでなくアート性も必要に。
- できるようになること
- トップレベルのネイリストとして必要とされる総合的な技術及び知識を修得していることを証明できる資格です。
JNAジェルネイル技能検定初級
- 受験料
- 9,900円
- 受験資格
- 義務教育を修了していれば誰でも受験可能
- 試験開催日
- 6月、12月の年2回
- 試験会場
- 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡
- 試験内容
- ネイルに関する基礎知識、およびジェルネイルに関する基礎知識が問われます。ネイルケアのベーシックをマスターすること、およびジェルネイルを施術するために必要な基礎知識・技術を習得することを目的とします。爪の構造や爪のトラブルといった、JNECネイリスト技能検定とも共通する内容が出題されるため、ネイリスト技能検定3級以上を取得している人ならば実技試験の第一課題が免除されるという条件があります。
JNAジェルネイル技能検定中級
- 受験料
- 13,200円
- 受験資格
- JNAジェルネイル技能検定試験 初級合格者
- 試験開催日
- 6月、12月の年2回
- 試験会場
- 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡
- 試験内容
- ネイルのケアとジェルネイルの施術をするために、サロンワークに必要な専門的な知識・技術の修得を目的とします。筆記に関しては初級と同様の範囲に加え、衛生と消毒、実践的施術に関する内容が追加されます。実技試験は、ジェルカラーリングに加えてポリッシュオフ・ジェルオフ・フレンチカラーリングといった施術が追加されます。
JNAジェルネイル技能検定上級
- 受験料
- 16,500円
- 受験資格
- JNAジェルネイル技能検定試験 中級合格者
- 試験開催日
- 6月、12月の年2回
- 試験会場
- 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡
- 試験内容
- ジェルネイルのスペシャリストとして求められる総合的な知識・技術の修得を目的とします。上級試験には初級・中級と異なり筆記試験がなく、実技試験のみというのが特徴的。与えられたテーマに沿って、ラメやストーンを用いたアートを施します。
ネイルサロン衛生管理士
- 受験料
- 10,560円 ※JNA会員の場合は6,160円
- 受験資格
- 年齢が18歳以上の方
- 試験開催日
- 毎月開催
- 試験会場
- JNA認定校
- 試験内容
- 安全で安心なネイルサービスの普及と公衆衛生の向上のために、ネイルサロンの衛生管理に関する知識を習得することを目的とします。認定校で実施される講習会に参加し、その上で筆記試験に合格することで資格認定となります。他の資格試験と異なって毎月開催されるため、比較的取得のチャンスの多い資格です。
認定講師
- 受験料
- 26,400円 ※1次試験免除者は15,400円
- 受験資格
-
- ネイリスト技能検定1級に合格しており、受験日において1級合格認定日から1年以上が経過している方
- プロのネイリストとして実務経験のある方
- 受験申込時に、日本ネイリスト協会の個人正会員の方
- 年齢が20歳以上の方
- JNA認定校を卒業している方
- 勉強会と授与式に必ず出席できる方
- ネイルサロン衛生管理士の資格を取得している方
- JNAフットケア理論検定試験の資格を取得している方
- 試験開催日
- 春(3~4月)、秋(8~9月)の年2回
- 試験会場
- 東京
- 試験内容
- 日本ネイリスト協会のメンバーとしてネイルの普及と発展に努めることが認定講師の役割。試験自体は、実技試験と筆記試験、さらに面接試験も行われます。合格者は、イベント実行委員・検定試験の試験管・コンテストの審査員・各セミナーの開催といった活動をしてもらうことになります。受験資格が細かく定められており、受験も1次・2次と厳しく審査されるため、プロのネイリストとして認められるための登竜門とも言えるでしょう。
アメリカの資格
マニキュアリストライセンス
日本の資格だと、全国どこで受けても内容は共通。ただし、アメリカで働くとなると州によってライセンスが異なります。また、1つの州でしかライセンスを取得することができないという点も特徴。「ニューヨーク州でライセンスを取得したけど、将来的にはハワイで働きたい」ということができないのです。しかし、日本と違ってアメリカのライセンスは国家資格なので、取得できれば身分証明の代わりにもなりますよ。
アメリカのマニキュアリストライセンスは、「受験料」「受験資格」「試験会場」なども州によって大きく異なるため、まずは自分がどこで働きたいのかを決めてからライセンス取得の準備を進めましょう。「永住権」や「社会保障番号(SSN)」などが求められる州もあり、条件は厳しいですが、海外でのライセンス取得をサポートしてくれるサロンもあるので、頼ってみてはいかがでしょうか。
その他、ライセンス取得で大きな壁となるのが、州の規定の美容学校へ進学することではないでしょうか。アメリカで働くためのマニキュアリストライセンスを取得するには、決められた履修時間をクリアする必要があります。例えば、カリフォルニア州でマニキュアリストライセンスを取得するには400時間、ニューヨーク州であれば250時間のプログラムを終了させなければなりません。日本でも専門学校やネイルスクールがあるように、アメリカでもネイリストのための学校が沢山あるのですね。
ネイリストの資格・検定の受験費用
資格取得にかかる費用
それぞれの資格を取得するために必要な費用をまとめてご紹介します!ここで紹介するのはあくまで受験料のみの金額。試験の勉強をするためのテキスト費用や通信講座を受講するための費用は別途必要になるので、注意して下さいね。
- JNECネイリスト技能検定3級:6,800円(税込)
- JNECネイリスト技能検定2級:9,800円(税込)
- JNECネイリスト技能検定1級:12,500円(税込)
- JNAジェルネイル技能検定初級:9,900円(税込)
- JNAジェルネイル技能検定中級:13,200円(税込)
- JNAジェルネイル技能検定上級:16,500円(税込)
- ネイルサロン衛生管理士:10,560円(税込)※JNA会員の場合は6,160円
- 認定講師資格試験:26,400円(税込)※1次試験免除の場合は15,400円
ネイリストの資格試験や検定は何歳から受験可能?
ネイリストの資格には、年齢制限が設けられていないものがほとんど。まずは、それぞれの資格の受験資格を見てみましょう。
- JNECネイリスト技能検定3級
- 義務教育を修了している人
- JNAジェルネイル技能検定初級
- 義務教育を修了している人
- I-NAIL-Aネイルスペシャリスト技能検定試験A級
- 義務教育を修了している人(未修了の場合、保護者の承諾書を提出)
- ネイルサロン衛生管理士
- 年齢が18歳以上の方。実務は不問
義務教育を卒業となると、中学校を卒業していればOK!ネイルサロン衛生管理士に関しても、特に学歴に関する条件はないため、年齢が18歳を超えていれば中卒・高卒でも問題なく受験をすることができますよ。また、いずれの資格も特にネイリストとしての経験は必要ないため、義務教育卒業という条件さえ満たしていれば誰でも受験にチャレンジすることができるのです。
その他にも、性別や年齢の上限が設けられていません。ネイリストというと20代~30代の若い女性をイメージするかもしれませんが、もちろん50代の男性が受験をしてもOKです。最近ではメンズネイルの需要も高まってきているので、男性ネイリストの受験者も増えてきています。
子育てをしながら自宅ネイルサロンを始めたいママさんや、会社を定年退職して趣味でネイルを始めたいシニア層でも挑戦しやすいのがネイリストの資格なのですね。
ネイリストの資格を取得するには?
ネイリストの資格を取りたい!と思いついた時には、少しずつ資格取得の準備をしていきましょう。ここでは、資格取得までのプロセスをご説明します。既に、ネイルサロンに勤めている人であれば、先輩スタッフに資格について質問してみても良いでしょう。初心者だからといって、諦める必要はありません。
1.どんな資格があるか調査
まずは、ネイリストに関する資格について下調べを始めましょう。難易度や必要となる技術、受験費用や受験会場など、調べる事は沢山ありますよ。ほとんどの資格は、一番簡単な所からチャレンジしていく事になるので、上級者となるまでコツコツと資格を取得していきましょう。
2.取りたい資格を決める
ネイリストとしての基礎知識を学びたい人は、ネイリスト技能検定。ジェルネイルのスキルを身に付けたい人は、ジェルネイル検定といったように、目的に合わせてチャレンジする資格を決めましょう。目指す資格が決まらないことには、ネイルスクールのカリキュラムも選べないので、きちんと決めておきましょう。
3.どんな学習方法があるか調査
仕事をしている人や学校に通っている人、家事や育児をしている人など、置かれている状況はさまざまです。その中で、自分に合った学習方法を見つけるのがポイントです。無理をして取ると、プレッシャーだけが残りネイルを楽しめなくなってしまいます。「自分にはどんな学び方が合っているのかな…」と、ゆっくり考えてみてくださいね。
4.スクールや講座を調査
ネイル技術を学ぶ方法として、ネイルスクールに通うという方法があります。ネイリスト認定講師がカリキュラムに沿って授業を行い、定期的に模擬試験を行うなど、スクールの方針で決められています。通うのが難しい人は、通信科に入学するのもおすすめです。チャットでのサポートやオンライン授業など、自宅からでも十分に勉強できますよ。
5.知識と技術を習得
勉強方法を決めたら、ひたすら勉強と練習を繰り返します。ネイリスト資格に最も必要なのは、決められた時間で完成させられること。技術があれば良いというわけではないのです。小さなミスは減点となりますが、タイムオーバーは、失格となってしまうのです。減点ならまだしも、失格となればそれまでの努力も水の泡。ストップウォッチを使って、工程ごとに時間を計りながら反復練習してくださいね。
6.資格試験会場へ
試験当日を迎えたら、時間にゆとりをもってでかけましょう。試験の内容でもありますが、忘れ物や遅刻、マナー違反は失格となります。ネイリストの試験では、ハンドモデルに同行してもらう必要があるので、モデルにも当日のルールを伝えておくようにします。まずは、実技試験を受けてから、筆記試験を受けます。非常に多くの人が、同じ会場で一斉に受験するので、まわりの人に惑わされないよう集中力を高めておきましょう。
7.合格通知を待つ
試験を受けてから合否の発表まで1ヶ月程かかります。受験票に記載した住所に、合否の通知が届くので、発表時期にはポストを確認しておくようにしましょう。また、資格試験を主催する協会のホームページでも合否の発表がされるので、受験番号を入力して調べてみると良いですよ!
ネイリスト資格・検定の勉強方法
資格を取得するためには、以下の3つの方法があります。それぞれの方法の特徴やメリットを知って、自分に合った方法を選択してみてくださいね。
- スクールに通って勉強する
- 通信講座を契約し、独学で勉強する
- テキストを購入し、独学で勉強する
学校(ネイルスクール)に通って勉強する
それぞれの都道府県に、ネイリスト資格が取得できる学校が多数存在します。中には、ネイルサロンで独自に運営しているような小さな学校も。趣味としてネイルを始めて、ゆっくり時間をかけて資格取得をしたいという方はどんな学校を選んでもOK!ただ、「確実にこの時期までに資格取得を目指したい!」と決まっている場合には、認定講師が在籍している認定校を選択すると良いでしょう。
学校で学ぶ場合には、ある程度の費用が必要になります。安価な学校でも20~30万円程度は用意する必要があると考えておきましょう。
- メリット
-
・講師がいるため、わからないことはすぐに質問できる
・決められた期間内に、全ての勉強を終わらせることが出来る
・資格取得後の就職サポートがあることも
・確実な知識や技術が身につく
学校に通う場合の期間と費用
まずはネイリストの学校に通う期間について。検定試験の受験を目的とする場合には、最短3か月で卒業できる学校もあります。受験日の約3か月前に入学して筆記の座学や実技のアート練習をしながら、検定受験を迎えます。ただ、選ぶ学校によっても卒業までの期間は異なりますし、もちろん通える頻度によっても大きく異なります。実際にネイリストや他の仕事で働きながら通う場合には、通常の1.5倍程度の期間が必要になると見ておいた方が良さそうですね。
続いては費用に関して。一般に、ネイリストの学校に通うとなると100万円以上の費用が発生することもあります。入学金を設定している学校が多く、その他にも取得したい検定級によって授業料が異なってきます。「検定の取得はしなくて良いから、自宅で趣味として楽しめるくらいのネイル知識を学びたい」という場合は、半額の50万円程度で通える学校も多くありますよ。
ネイルの学校を選ぶポイントは?
学費だけではなく、その他にも「授業の日程」「認定校かどうか」「通いやすさ」といった点も、学校選びの大きなポイントと言えるでしょう。どれだけ学費が安くても、自分が受けたい授業が自分の通える時間に開講していなければ意味がありません。また、JNA認定校かどうかも入学前にチェックをしておきましょう。
JNA認定校とは、ネイリストを教育する施設として日本ネイリスト協会に認められた学校のこと。「カリキュラム」「講師」「施設」といった面で認定校としての規定をクリアしているので、学校選びの際には参考にしてみて下さいね。
関連記事:自分に合ったネイル学校の選び方
通信講座で勉強する
送られてくるテキストやDVDに沿って、自分のペースで勉強を進めていくという方法。スクールに通って勉強するよりは費用を安価に抑えることができますし、公式テキストを購入して完全に独学で進めるよりは安心して勉強ができるという特徴があります。「スクールに通う時間はないけれど、決められたカリキュラムで勉強をしたい!資格取得の期日が決まっているわけではないから、自分のペースで勉強したい!」という人に向いています。
- メリット
-
・自分で時間を決めて勉強ができる
・スクールよりも安価で勉強ができる
・スクールよりも短い時間でテキストを終わらせることができる
通信講座で学ぶ場合の期間と費用
ネイリストの通信講座学ぶ際に、どれくらいの期間が必要になるのでしょうか。これは、選ぶ講座によって大きく異なるので一概には言えません。通信講座は自分のペースで学習を進めていくもののため、効率よく勉強を進めれば1検定につき3か月程で終えることが可能なものも。ただ、添削されて返ってくるまでに数週間の時間を要することもあり、自分の勉強スピードがどれだけ早くても添削スピードに左右される場合があります。
1つの通信講座で2つ以上の検定に関して勉強したいという場合は、前述した期間の倍である半年程の期間が必要と考えておくと良いでしょう。あくまで目安の期間のため、それよりもスローペースで勉強をすることももちろん可能。ですが、講座によってはサポート期間の上限日数が決められていることもあるため、注意して見ておく必要がありますよ。
ネイルの通信講座を選ぶポイントは?
通信講座を選ぶ上で、最も重要視したいポイントは「サポートの充実さ」ではないでしょうか。学校に通う場合には対面で講師から指導を受けることができますが、通信講座となるとそうはいきません。スクーリングの開講数や添削スピード、添削の丁寧さといった点をしっかり調べて、口コミも参考にしながら選ぶと良いでしょう。
その他にも、テキストの内容ももちろん大切です。通信講座で勉強していくにあたって、メインで使用するのがテキスト。基本的には自分1人で勉強することが求められるので、内容の充実さだけでなく、自分が見やすい構成のテキストであるかも見た上で選びましょう。
さらに、どこのサロン・企業が運営している通信講座なのかもしっかり見ておくべきポイント。学校に通う時と同様に、認定校のサロンが運営している講座であれば安心して受講することができますよね。多少価格が高かったとしてもサポートや知名度、過去の受講者実績などを比較して、自分が一番納得できる通信講座を選択しましょう。
関連記事:通信講座でネイリストを目指す!
独学で勉強する
協会から発行されている公式の問題集を購入したり、市販のテキストを購入したりして独学で勉強をするという方法。かかる費用はテキスト代だけなので、1万円以下で勉強ができることも多く、サロンワークや育児とも両立させやすいでしょう。既にネイリストとしての経験がある場合、実技の練習はサロンの先輩に付き合ってもらって、筆記の勉強だけは家でしたいという方も多いはず。筆記で出題される問題は、例年そこまで大きく変更になることはありません。そのため、過去の問題集や公式問題集を解いて対策することができます。
- メリット
-
・テキストを購入したら、その日からすぐに勉強を開始できる
・スクールや通信と比べても非常に安価で、数千円で購入できるテキストが多い
・サロンワークと両立して勉強をすることができる
スクールに通うとなると、勉強や練習の時間をしっかりと確保できるというメリットがあります。ただし、ネイリストとしての実践的な経験を積むことができないというデメリットも。それに対し、通信講座で学ぶ方法やテキストを購入して学ぶ方法であれば、実際にネイリストとしてサロンワークを行いながら勉強をすることが可能になります。「必ず資格を取得する!」という強い意志があるならば、時間に融通が利く独学での取得を目指してみても良いですね。
独学の場合には、「〇月〇日の試験までに、1日2時間勉強する」「〇日までにテキストを全て読み終えて問題集を解き始める」といった具体的な数値目標を定めておくと◎勉強のスケジュールもしっかり組んでから着手するようにしましょう。
独学で学ぶのにおすすめの本(テキスト)
「独学で勉強するにしても、何を見て勉強したら良いのかわからない…」なんてこともありますよね。一部ではありますが、資格取得のための本をご紹介します。
【NPO法人日本ネイリスト協会(JNA)監修】- ネイリスト技能検定 1級・2級・3級 完全対策バイブル
- JNA テクニカルシステム ベーシック
- JNA テクニカルシステム ジェルネイル
- ネイリスト技能検定試験 公式問題集
このように、日本ネイリスト協会(JNA)や日本ネイリスト検定試験センター(JNEC)が監修する教材が発売されています。これらの本は、筆記試験対策にも一役買ってくれますよ。また、付箋を貼ったり単語帳を使ったりして、ネイル用語をしっかり覚えましょう!
独学で学ぶ場合の期間
全くの未経験者か、ある程度のネイルの知識があるのかによっても期間は異なってきます。全くネイルの知識がないという場合には、通常取得のために必要と言われている3か月の倍の期間、半年程を見ておきましょう。(ネイリスト技能検定3級の場合)未経験者の場合には、筆記の勉強よりも実技の練習を何度も重ねることが大切。検定では制限時間が設けられるので、手に覚えこませて緊張をせずに本番を迎えられることが必須です。
また、ある程度ネイルの経験がある方は筆記の勉強を重点的に。「普段働いているからネイルの知識は頭に入っているはず!」と思っていても、意外と知らない言葉が多く出題されます。普段のサロンワークでは問われないような知識も多いので、少なくとも1か月は毎日テキストを見て勉強してくださいね。
ネイリストの資格取得・検定合格までに要する時間
続いては、それぞれの資格を取得するためにどれくらいの期間が必要なのかをご紹介します。勉強に割く時間は人それぞれなので一概には言えませんが、目安として取得するまでに以下の期間は必要になると考えておきましょう。
- JNECネイリスト技能検定3級:3か月程度
- JNECネイリスト技能検定2級:6か月程度
- JNECネイリスト技能検定1級:1年程度
- JNAジェルネイル技能検定初級:2~3か月程度
- JNAジェルネイル技能検定中級:6か月程度
- JNAジェルネイル技能検定上級:6か月~1年程度
JNECネイリスト技能検定とJNAジェルネイル検定の場合、筆記の内容は重複している部分も多いため、両方取得したいと考えている人は同時期に勉強を開始すると効率的かもしれません。出題範囲が似ているからといって、ネイリスト技能検定取得から数年間勉強せずにジェルネイル検定に挑むと、「あの時覚えたけど忘れてしまった…」ということになりかねないので注意が必要です。
- ネイルサロン衛生管理士: 2~3か月程度
- 認定講師資格試験:3か月程度
ネイリストの資格の場合、筆記の勉強時間も大切ですが実技の練習の時間もとても大切です。テキストを読みながら勉強するのではなく、実際に手を動かして施術をしてみるのが一番です。
ネイリストの資格の難易度
ネイリストの資格は、受験したあとに合格率が発表されています。日本ネイリスト検定試験センター(JNEC)のネイリスト技能検定試験を参考に難易度を見ていきましょう。ホームページでは、「受験者数・合格者数推移」が更新されていきますので、参考にしてみてくださいね。
| 2022年秋期 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 2,822 | 1,446 | 51.2% |
| 2級 | 3,515 | 2,105 | 59.9% |
| 3級 | 8,203 | 7,431 | 90.6% |
| 2023年冬期 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2級 | 3,041 | 1,695 | 55.7% |
| 3級 | 5,066 | 4,533 | 89.5% |
1級は年に1回、2級と3級は年に2回、開催されるネイリスト技能検定試験。3級は、8~9割合格しているのに対して、1級と2級の合格率は5割程度に下がっています。2人に1人は落ちているという計算になります。義務教育を受けた人であれば、受験することができる3級に対し、1級と2級は、3級合格者であることの他にも、サロンやスクールでの技術練習が必要なのかもしれませんね。
ネイリストの資格を取得するメリット
専門知識と高い技術を持ち信頼される
資格を取得することで、専門知識と高い技術を習得することになりますので、お客様からも信頼されるようになります。爪まわりのトラブルや悩み事なんかも相談されるようになるでしょう。また、サロンを開業したばかりでも、十分なスキルを持っているということをアピールできますよ。
就職活動の際に履歴書へ記入できる
就職活動で最も大事なのは、自分の能力をしっかりアピールできるかどうかです。ネイルサロンに就職する時に資格を持っていることで、能力のアピールにもなりますし即戦力として働くことができるのです。
ネイリストの資格で、最も受験者数の多いJNECネイリスト技能検定の公式HPによると、履歴書に記載できる級数に関しては「特に制限していませんので、何級合格からでもお書きいただけます。」とあります。そのため、3級を取得した時点で、そのことを履歴書に書いてもOK!記載する場合には、「ネイル検定3級」と省略した名称ではなく、「JNECネイリスト技能検定3級」というように正式名称で記入をしてくださいね。
検定級が高くなるにつれ就職活動で有利に働くのは大前提ですが、目的に合わせて資格を取得しても良いでしょう。サロンの店長や経営に興味がある場合には、「ネイルサロン衛生管理士」の資格も取得しておくと衛生管理に関する知識があることをアピールできますし、何より経営側にも興味があるという点をアピールすることができます。
給料アップに繋がる可能性がある
ネイリストになるのに資格は必須ではないとはいえ、技術が身についたことの証になるのが資格です。多くのネイルサロンが入社の応募条件に「ネイリスト技能検定2級程度の技術や知識を持っていること」と掲げています。さらにネイリスト技能検定1級、ジェルネイル検定上級、JNA認定講師などの資格を持っていればキャリアアップや収入アップの強い味方になるでしょう。高収入ネイリストを目指すなら、JNECネイリスト技能検定1級の資格は取っておきたいところです。
また、ネイリストの収入アップには指名料も大きく関係してきます。サロンによっては指名料バックがあったり昇給昇進の目安になったりと、指名率が上がるほど収入は上がっていくと言えます。独立開業する際も、それまで指名してくれていたお客様の数がその後の収入に大きく影響します。高い技術を持ちながらお客様との信頼関係を築くことで、自然と指名される回数も増えていくのではないでしょうか。
関連記事:資格取得のメリットとは
ネイリストの資格がないと就職できない?
ネイリストの資格は国家資格ではないため、資格を持っていなくてもネイリストになることはできます。とはいえお客様にネイルアートを施すためには高い技術が求められますし、ポリッシュやジェルネイルなどネイルには様々な種類があるのでそれを上手く使うための知識も必要です。
また、ネイリストのお仕事はネイルアートを施すだけではなく、甘皮のケアや爪に関するトラブルへのアドバイスを行うなど、爪の健康全般に関する仕事も含まれています。資格を取得することで、ネイルアートだけではなく爪のケアに関しても学べるので、信頼のおけるネイリストと評価されますよ。ネイリストの資格取得を目指しつつ、ネイルサロンへの就職活動もしていくと良いでしょう!